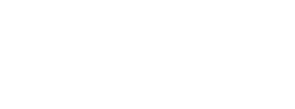【保護者向けコラム】焦る気持ちとどう付き合うか
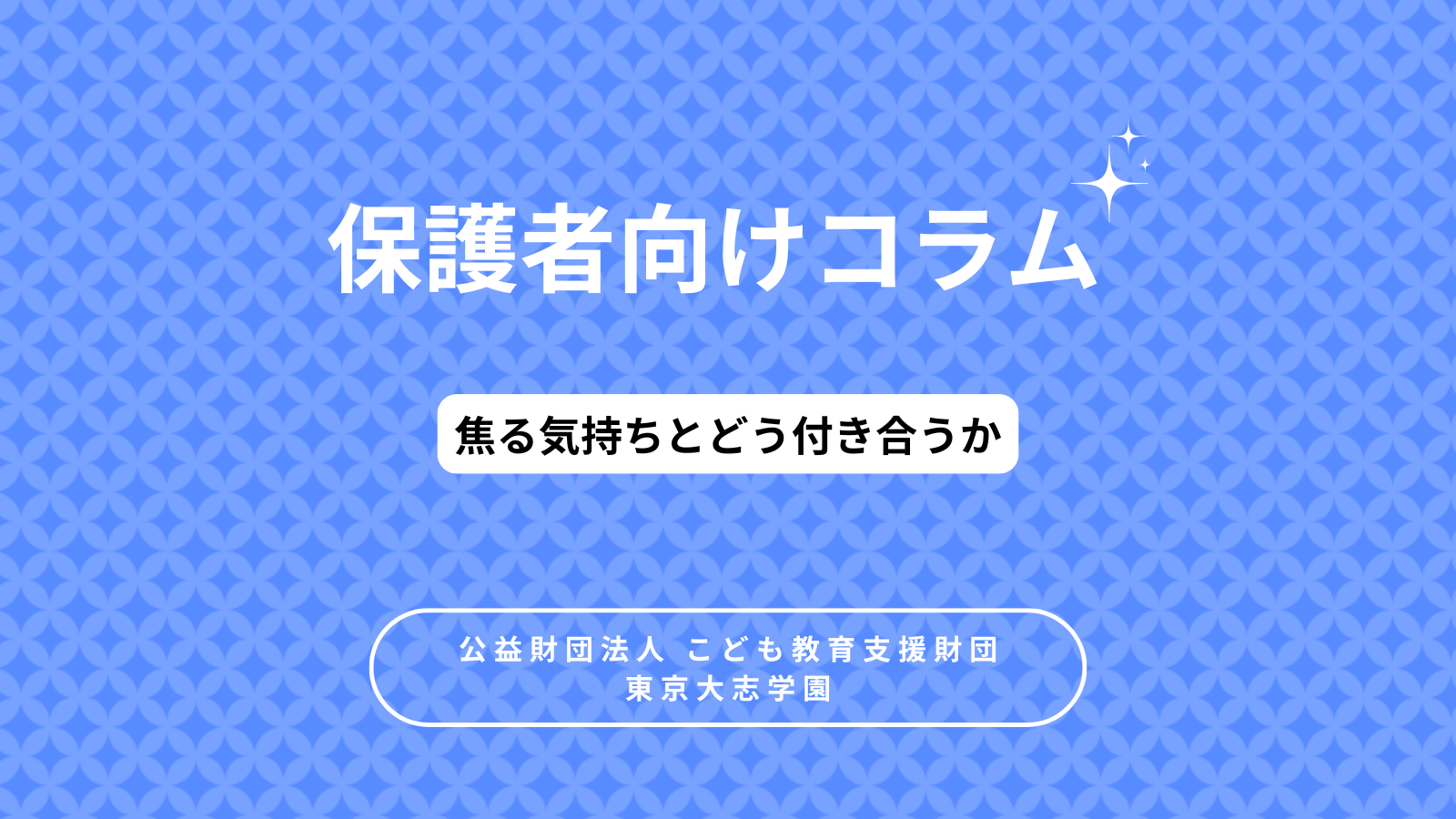
不登校が続くと、「このままで大丈夫?」「いつになったら学校に行けるの?」と、焦る気持ちが湧いてくるのは自然なことです。
親だからこそ、子どもの将来を思えば思うほど、その焦りは大きくなりますよね。
でも、その焦りが強くなりすぎると、つい「早く」「どうして」と子どもを責めてしまい、親子の気持ちがすれ違ってしまうこともあります。
今回は、そんな焦りの気持ちとどう向き合えばよいのか、3つの視点から一緒に考えてみましょう。
視点①:私の焦りはどこからきているのか?
まずは、自分の焦りの“出どころ”に目を向けてみましょう。
子どもが学校に行かない理由がわからないから?
子どもが将来のことを考えている気配がないから?
家族が他人事のように感じてしまうから?
焦りの背景にある思いや不安に気づくことで、今できることが見えてくるかもしれません。
視点②:焦ることは悪いことなのか?
焦る気持ちは、決して悪いものではありません。
それは「なんとかしたい」という前向きな気持ちの表れでもあります。
人の気持ちは、常に落ち着いていることはありません。波もあります。
焦る自分は頑張っている証拠と思い、ご自身をいたわってみてください。
ただ、強い焦りは、自分にも周りにも負担をかけてしまうので、少しでもやわらげたいですよね。
≪焦りをやわらげるための小さな工夫≫
・「私、いま焦っているな」と心の中で言葉にしてみる
・深呼吸をして、気持ちをリセットする
・いまの目の前の作業に集中してみる
また、地域や民間の相談機関などで、自分の思いを話すことも、気持ちの整理にとても効果的です。
視点③:子どもは焦っていないのか?
一見、焦っていないように見える子どもも、実は心の中では焦りでいっぱいになっていることがあります。
たとえば:
・ごろごろして漫画ばかり見ている
・「朝起きる」と言って寝たのに、起きてこない
そんな姿にイライラしてしまうこともあるかもしれません。
でも、エネルギーが落ちているとき、人はやろうと思ってもできないことがあります。
子どもは、そんな自分を守るために、逆の行動をとってしまうこともあるのです。
保護者の方が安定した気持ちで接してくれることで、子どもの焦りも少しずつやわらいでいくかもしれません。
おわりに
焦りは、子どもを大切に思う気持ちの裏返しです。
その思いを否定する必要はありません。
大切なのは、焦りをそのまま子どもにぶつけず、いったん立ち止まること。
そして、焦っている自分を責めないこと。
今できる小さな一歩を重ねていけば、振り返ったときに、きっと大きな変化になっているはずです。